
挑戦者決定戦にふさわしい大熱戦でした
プロの実戦から学ぶために心がけること(自論)
他の将棋の勉強法もそうですが、ただただ漠然と棋譜並べ・観戦をしても非効率的です。
勉強法は手段であって、目的は棋力アップです。
棋力アップのためにどのような意図をもって手段を利用するかが需要なのです。
それではどのような意図をもって棋譜並べ・観戦に臨めばよいのでしょうか。
私は以下を心がけています。
- 序盤の工夫点(今までの前例との違い)
- 仕掛けの技術(開戦直後の十数手)
- 中盤の方針(攻めるのか受けるのか、その場合どこに目を向けるのか)
- 終盤の急所
それぞれの理由については別の記事で紹介します。
本局のサマリ
- 戦型は相雁木
- 先手の藤井竜王が右四間に振りなおし開戦
- 歩を使った小技の連続で終盤戦へ突入
- 豊島九段の中段玉に一度はもつれかけたものの、駒がぴったりで藤井竜王が
なんとか寄せ切る
序盤戦
【図】 14手目 ☖53銀右まで
早速後手の豊島九段の工夫が序盤から現れました。
雁木を狙ってますが、先手の出方によっては嬉野流の選択肢をとれるようにしています。
なぜ最初から雁木に囲わないかは、現時点で雁木は早繰り銀に押され気味だからです。
理由は別の記事で紹介します。
【図】 36手目 ☖51銀右まで
ここが後手の作戦の岐路です。
後手の角が退いたため、先手はこの後☗65歩から右四間飛車の形を作りました。
角のラインを生かして1筋、3筋、4筋を狙うわかりやすい展開。
ところで上の図から一手戻り☖64歩とした場合は、先手はどのような構想にするのか…課題局面です。
中盤戦
【図】 58手目 ☖87歩まで
角換わりっぽい手筋が飛んできました。
さて、☗同金と取るとどんな狙いがあるのでしょうか。
実戦では藤井竜王はこの歩を取りませんでしたが、もし取った場合は
以下のように進むと想定されます。
☗同金 → ☖85歩 → ☗同歩 → ☖93桂
この手筋は居飛車党には必須級の手筋なので覚えておきましょう。
この後はもちろん飛車で歩を取って、横に展開するパターンもありますし、
端を突き捨てて桂で狙う展開もあります。
桂と歩だけで手になる非常においしい手筋です。
終盤戦
【図】78手目 ☖37角成迄
さて、攻め駒が限られてますが、先手からはどのように攻めるのがよいでしょうか。
以下2つが考えられるでしょうか。
- ☗34銀
- ☗34歩
答えは実戦の進行通り1の☗34銀です。
先手玉はそんなに丈夫ではないので駒得より速さが求められます。
たとえば以下のような攻めが考えられます。後手勝勢です。
☖66歩→☗同銀→☖46桂→☗68金右→☖86飛
終盤は駒の損得より速度
耳タコだと思いますが、終盤はこの金言を心がけることが重要ですね。
以降一時は互角になる局面もありましたが、見事に藤井竜王が寄せ切り永瀬王座への挑戦権を
獲得しました!
まとめ
序盤の豊島九段の工夫は雁木を指したい方に流行るかもしれません。
また対策を練らねば…
今回は以上です!また別の記事にて
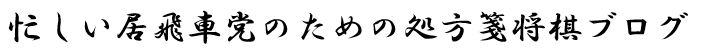



コメント